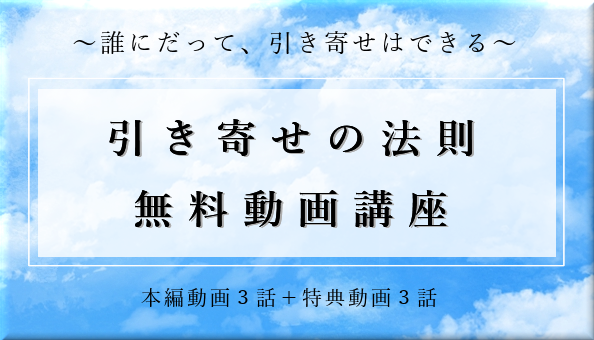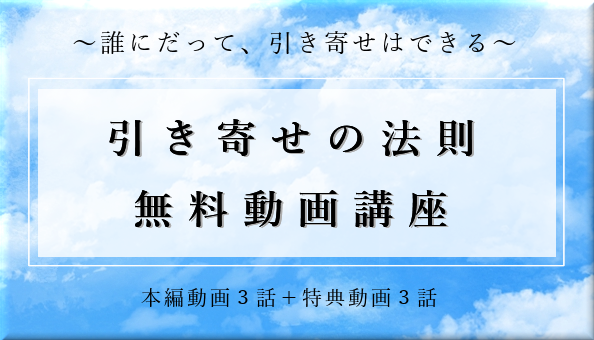潜在意識から不安が出てきたら大正解
本日は、アファメーション中に感じる不安についてです。
アファメーションをすると自分の潜在意識から、
「でも、どうせそんなことできない」
「どうせ私なんて…」
という不安や恐怖が出てきますよね。
そうすると当然、嫌だな~って思います。
でもでも実はこれ、
「そうして潜在意識から不安が出るのが大正解!ならないほうが何かが間違ってる」
んです。
その不安は、アファメーションする以前からあなたの潜在意識に潜んでいたものです。
別にアファメーションによって新たに出現したわけではなく、普段から、
意識はしていないだけであなたの心の底にはずっと、24時間365日潜んでる不安です。
普段は潜在意識下に潜んでいるから意識せずにすんでいるんだけど、
その潜在している不安って、なにかの折にポンと出てきて悪さするのであなたは困ります。
たとえば、好きな人と仲良くなりたいなと思ったときにポンと、
「でもどうせ相手にされないよ」
とか。
成績あげたいなと思ったときに、
「でも頭悪いし無理じゃん」
とかとか。
こうしてポン、ポン、と意識の上に出てきて邪魔をしてくるので、あなたは困ってしまいます。
こういう不安って、感じまいとして押し殺す人が多いのですが、
そうしてまた潜在意識下に追いやったところで、不安を消すことができたというわけではありません。
今のところは見えなくなった、というだけで、ずっと潜んで存在しているしまたいずれ出てきます。
こういう不安は根こそぎ退治して消すことができればいいですよね。
潜在意識下の不安をゴキブリに例えてみる
これ思ったんですが、
「意識はしていないだけで、あなたの潜在意識には24時間365日不安が潜んでいる」
を、
「気づいていないだけで、あなたの部屋には24時間365日大量のゴキブリが潜んでいる」
と例えたらどうかと。
そう、普段は隙間に潜んでるから気づかない・意識できないだけで、すっげーいるとする…怖いだろ…。
潜んでるゴッキーってたまにいきなり出てきてぎゃーってなりますよね。
たまに出てきて困ってしまう不安とちょっと似てます。
そこで一掃するためにバルサンを購入、部屋で焚くとする。
で、焚いたら苦しんだゴッキーがうぎゃーって部屋の隙間とかから大量に出てきてびびったとする。
(いや、普通はバルサン焚いてる間は部屋から出るし、実際焚いたら隠れてたゴッキーが隙間から出てくるかどうかはともかく、単なる例えとして)
出てきたらあなたはウッギャアアアアと動揺するかもしんないけど、でもなんで出てきたかというと、
ちゃんと退治しようとしたからであって、こちらのやり方がちゃんと相手に効いてるからこそ、効いている証拠として出てきますよね。
これと同じで、アファメーションってちゃんと効いているときに、その効いている証拠として不安が出てきます。
逆に、なんか間違ったやり方してると不安にならないです。
潜在意識を変えようとして、「できる」という言葉で刺激してゆさぶりをかけてるっていうのに、
そこで不安が出なかったら、それって潜在意識をうまく刺激できてない、反応させられてないってことです。
むしろ不安にならない場合に、
「なんかやり方違うってことだ、やばい、ちゃんとできてないんだ…」
と不安になったほうがいい。
なんだかへんな言い方なんだけど、
不安になったら安心してください、「私のやっていることは間違ってない証拠だ!」と。
「嫌だー、不安がでてきたー」と考えるより、
「しめしめ、あぶりだされて出てきやがった。効いてる効いてる♪」
と思ってみてください。
こうして出てきてくれるからこそ、それを退治して消すことができます。
出てきた不安はアファメーションで必ず退治できる
①不安が潜在意識の中に潜んで隠れてしまっている
②隠れているので退治しようにもうまいこと手が出せない
③いつまでも自分の意思とは関係なくちょいちょい意識の上に上ってきて困る
というのが今の状態なので、
①不安が潜在意識の中に潜んで隠れてしまっている
②意識の上まで不安をあぶりだす
②出てきた不安を「できる」という言葉でどんどん退治していく
どうでしょう、こういうふうに考えると少しは、
「アファメーションすると不安になるので嫌だ」
という気持ちは和らぐでしょうか?
「不安なのはアファメーションが効いている証拠だ」
「のこのこ出てきてくれたおかげで消せるぜ~♪」
と考えてみてください、きっとそっちのほうが楽だし、続けやすいと思います。
「潜在意識から不安が出てくるので嫌だ」ではなく「出てきたおかげで消せる!」と考えてみて。
無料の動画講座を開催中です
引き寄せについて、さらに詳しく動画で学んでみませんか?
引き寄せで誤解しがちな点の解説や、願いが叶いやすい願望設定の仕方などについてお話しています。
動画の詳細については以下からどうぞ。
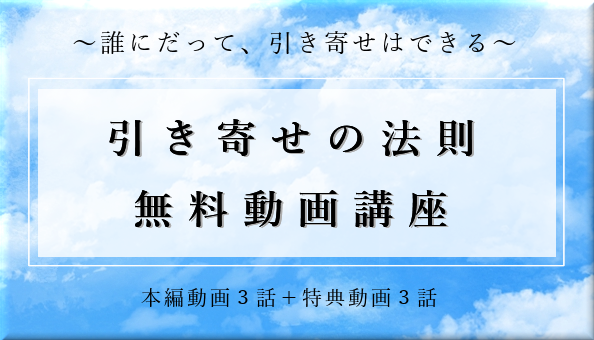

引き寄せでうまくいくには「自分を変える」ことが絶対の条件
本日はアファメーションについてです。
アファメーションって引き寄せですごくよく言われることですが、
引き寄せを実践している方って大きく分けると、
①アファメーションを避けてさまようタイプ
②アファメーションにとらわれて動けなくなるタイプ
の2種類に分けられるように思います。
今回は①のタイプの方についてお話してきます。
これは昨日の記事にも書きましたが、引き寄せの法則とは、
「自分の思考を『できる』へと変えれば、できます」
という法則です。
裏を返すと、
「自分の思考を『できない』から変えなければ、できません」
と伝えてきている法則でもあります。
引き寄せってもともと、
「あなたが自分の思考を変えるのであれば」という条件付きで、
うまくいきますよ~と言っている法則です。
ならば、こちらはその条件をクリアするしかない。
つまり引き寄せにおいては、
「自分を変える」という条件は、どうしても満たさなければならない絶対条件。
ということです。
そしてたいがいの書籍などでは、
「その条件をクリアするために(思考をできるへと変化させるために)この方法を使いなさい」
と、アファメーションが出てきます。
頻繁に言われすぎてむしろスルーされるようになったアファメーション
私は引き寄せについてよく知らなかった頃、
読む本読む本にアファメーションという言葉が出てくることに、
だんだんウンザリする気持ちになってきたのを覚えています。
「またこの本もアファメーションって言ってるわ、他に言うことないのかな…」
みたいな気分になってくるんです。
なんか徐々に、
「はいはい、わかったってば」
みたいな気分になってくる。
もはや最後のほうは、アファメーションについて書かれている章は読み飛ばすことさえありました。
「それについては嫌というほど読んでわかってるから、もういいわ」
と思うからです。
こういう方はほかにもいるかもしれないなと思います。
では、なんでこうもみんながみんな口をそろえてしつこくアファメーションとうるさいのか?
これは、
「それを言うしかないから」
なんですね。
どういうことかというと、人間の潜在意識って「刷り込み学習」しかしないんです。
何度も繰り返されたことしか覚えない、という特性がもともとある意識です。
なので、その特性を持った意識を変えたいのであれば、これはもう繰り返して刷り込んでいく以外、すべがないんですね。
①海に行きたい
②海に行くための手段はバスしかない
③ではバスを使うしかない
これと同じで、
①潜在意識を変えたい
②潜在意識を変えるための手段は刷り込みしかない
③では刷り込むしかない
です。
「海に行きたいのですが…」と言う人がいれば、手段がバスしかない以上、
言われた側は「バスを使って」と答えるしかないですがそれと同じで、
「潜在意識を変えたいのですが…」と言う人がいれば、
言われた側は「変えたい内容を繰り返して」と答えるしかありません。
それを言うしかないため、引き寄せについて教える本などには「アファメーションしなさい」と書かれていますし、私もそう言っています。
しかしなんだろう、私はここ最近自分がアファメーションと書くたびに、
「健康を大切に」
という言葉が脳内に浮かんできます。
①健康でいたい
②健康でいるためには健康を大切にするしか手段はない
③では健康を大切にするしかない
なので「健康を大切に!」と世では言われていますが、
もうこの言葉って耳タコ状態というか、そんなこと言われなくてもわかってる、みたいな気になりません?(^^;)
でも実際には、わかってないから暴飲暴食とかするわけです。
そんで病気になって、そこで初めて「体を大切にすればよかった」と気づいたりしますよね。
これと同じで、なんか引き寄せが流行るほどにアファメーションという言葉も一緒に流行ったので、
健康を大切に、と言われたときと同じような反応になってる方も多いんじゃないかなと思います。
そんなこと言われなくてもわかってる、みたいな感じでスルーする人が(私を含め)増えてる気がします。
でも実際、わかってないからやってないわけです。
そんで死ぬときになって、「願いが叶わなかった」とか気づいても遅いんだぞ~!( ゚Д゚)
引き寄せでうまくいかない人の流れは大体こんな流れ
私はよく「自分を変えるにはどうすればいいですか?」と質問をいただきます。
上に説明したように、変えるためのすべは刷り込み学習しか存在していないため、
「アファメーションを繰り返してください」
と答えます。
すると相手から、
「…やっぱり、それしかないんですかね…?」
と返ってくることがあります。
そう聞き返したくなる心情は、だいたいこんな感じなのかなと思います↓
①「できると信じればうまくいく!」と言っている引き寄せの法則、発見!
↓
②「へぇぇ!できると思うだけでいいんだ!楽そうだ、やってみるか!」
と興味を持つ
↓
③しかし、やれと書かれているアファメーションをやってみたら、思っていたより面倒で辛い
↓
④「ちぇ、なんだよ…楽そうだからやってみようと思ったのに…面倒じゃん…。
…なんとか、アファメーションしなくてもうまくいく方法ってないのかなぁ…」
と思い始め、アファメーションをやめてしまう。
↓
⑤しかし実際のところ、残念ながら自分を「できると思考している人間」に変えるにはそれ(刷り込み学習)しか方法がない。
その唯一の方法を使わないため、「できると思考する」という絶対条件を満たすことができず、ずっと変われない。
↓
⑥「変われません、どうすればいいですか?」と私に質問する。
↓
⑦私は「アファメーションしてください」と答える。
↓
⑧言われた側は、
「えー…。…それをするのが嫌だから、暗にそれ以外のことが聞きたいって意味でどうすればいい?って聞いたのに…」
と思う
↓
⑨「やっぱり、アファメーションするしかないんですかね…?」
と、本当に他に何かないのか改めて確認したくなる。
という感じだと思います。
正直、その気持ちもわかります。
でもね、これちょっと…もしあなたがこういう立場だったら?と想像してみてほしいんです。
①「海に行きたいんですが、どうすればいいですか?」と誰かに声をかけられる
↓
②あなたは海に行くための手段がバスしかないと知っている。
そのため「バスに乗ってください」と答える。
↓
③「えー…。…それをするのが嫌だから、暗に他の方法が知りたいって意味で聞いたんですけど…。…やっぱ、バスしかないんですかねぇ?」
と聞き返される。
どうでしょう、こう言われると、
「…素直にバスに乗って…」
という気持ちにならないでしょうか。
私はそのような心境になるわけです、素直にアファメーションして…と…。
目的は「願いを叶えること」か「願いを叶える方法から逃げること」か
こういう方っていつの間にか目的が、
「願いを叶えること」
から、
「アファメーションを避けて通ること」
にすげ変わってしまっていることに自分で気づいていないんじゃないかな、と思います。
本当の本当の目的は、
「自分の願いを叶えるために、アファメーションという手段を用い、自分を変える」
ということですよね。
それがいつの間にか、
「アファメーションが嫌だから、アファメーション以外の方法を探し、自分を変える」
に変わっていないかどうか、確認なさってみてください。
もしそうなってたとしたならば、私自身もそうだったのでほんっとう~~~にその気持ちはよくわかるんですけども…(;^ω^)
でもね、そうしてアファメーションしないことが目的なら、
いまあなたの目的は達成されて、すでに叶ってるということになるんです。
アファメーションを避けて通りたいと思考し、そしていま実際にやらずに避けているのであれば、
それってちゃんと思ったとおりにできている、ということです。
本当にそれでいいのかな?って、もう一度自分に問いかけてみてください。
ときにそのものズバリ、
「アファメーション以外の方法で潜在意識を変える方法ってありますか?」
と聞いてくる方もいます。
ある意味、
「まぁそれが本音だろうな、この人素直だな」
とも思うのですがこの質問って、
「潜在意識を変える方法を使わずに、潜在意識を変える方法ってありますか?」
と聞いているということです。
それは、
「海に行くための方法を使わずに、海に行く方法ってありますか?」
と聞いているのと同じで、こう言われると、
「さすがにそんな方法はないな…」
って、気づくかと思います。
「願望達成」という目的を達成するための手段として「アファメーション」を使います。
いつの間にか目的が「願望達成のための手段を避けること」になっていないか確認してみてください。
願望達成のための手段を避けていたら、残念だけどそりゃ願望達成されないからね…(;´・ω・)
あなたの目的は「願望達成」のはず。
「アファメーションを避けること」が目的になっていないか確認を。
無料の動画講座を開催中です
引き寄せについて、さらに詳しく動画で学んでみませんか?
引き寄せで誤解しがちな点の解説や、願いが叶いやすい願望設定の仕方などについてお話しています。
動画の詳細については以下からどうぞ。
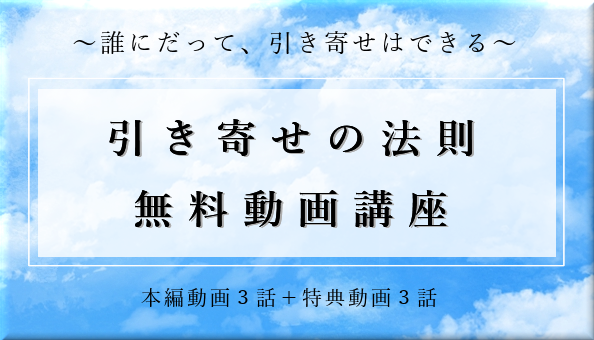

宇宙へのお願いは引き寄せにおいて必須ではない
本日は「宇宙にお願いしても効果がない」という方へのお話です。
「波動を上げようと頑張っているんですけど、良いことがありません」
「宇宙を信じて祈ってるはずなのに、悪いことが続くんですけど…」
といった方にぜひご覧になっていただきたい内容です。
「私はできる」と思えるか否かが肝心
私は特に、宇宙にお願いをして願いを叶えたことはありません。
ただ、
「宇宙のパワーなんかないぞ、だから宇宙にお願いしても効果ないんだぞ」
とか言うつもりも、まーーったくないです。
そんなことは全くもってない、心から宇宙を信じた人は必ずうまくいきます。
これに関してはこの記事に書きました。
記事の内容をまとめると、
- 引き寄せは思考が現実になる法則
- 「うまくいくという思考」がある以上、必ずそれは潜在意識の力で現実になる
- 「うまくいくという思考」を持てるのであれば、持てるようになる手段はなんでもいい
というものです。
つまり肝心かなめの部分は、
「私はうまくいくのだ、と思考できているか否か」
であって「宇宙を信じるか否か」というところではないので、
信じてようが信じてなかろうが、どっちでもいいんです。
「宇宙のパワーは絶対にある!!だから絶対にうまくいく!」
でも、
「引き寄せにはしっかり科学的根拠がある!だから絶対にうまくいく!」
でも、
「うちで飼ってる犬は超すごいパワー持ってる特殊犬だから、飼い主の俺には恩恵を与えるはずだ!だから絶対にうまくいく!」
でもなんでも、とにかく根拠はなんだろうが構わない。
要は「うまくいくという思考」を持てさえすればうまくいくのが引き寄せです。
宇宙を「信仰しろ」であり「依存しろ」ではない
「宇宙にお願いしているのに効果がない、叶わない」
という人は結局のところ、
肝心の部分の「うまくいく」という思考を持てていないからうまくいかないんです。
ではでは、
- 宇宙にお願いしてうまくいくという思考を抱ける人
- 宇宙にお願いしてもうまくいくという思考を抱けない人
この2つって何が違うの?というと、
宇宙を信仰しているか、依存しているか。
の違いだと思います。
多分、こんな感じじゃないでしょうか?
たとえば受験の前になって神社に合格祈願に行ったとき、
- お願いをしたのだから、きっと神様が見守っていてくださる!と神に全幅の信頼を置いて、安心して勉学に励めるようになった→合格する
- お願いしたんだから、ちゃんと叶えてくれるんだろうね!?と疑いの気持ちを持ち、ちゃんと自分が合格させてもらえるかどうかばかり気にして勉強がおろそかになる→不合格になる
こういう違い。
前者のほうは合格後、
「やはり神様が見守っていてくださったのだなぁ…ありがとう…」
と思いますよね。
以前よりますます神を信頼し、感謝します。
ますます「神」という存在がその人の力になり、神を信じることでうまくいくようになります。
後者のほうは不合格後、
「ちゃんとお願いしたのに効果なかった。なんで合格させてくれなかったわけ?」
と、神を疑い、不満を抱きます。
もとよりさして神を信じていないのに、ますます神を疑う気持ちが強くなり、
ますます「神」という存在がその人にとって信頼できないものになり、いつまでも神を信じることではうまくいかなくなってしまう。
「宇宙を信じてください」という書籍はたくさんありますが、
そこには「信じなさい」とは書いてあっても、「依存しなさい」とは書かれていないはず。
あくまでも「信じなさい」です。
それは、「本物の信仰心を持て」とか「心からの敬愛や畏怖を持て」という意味です。
そういった篤い信仰心を持ったならばうまくいきます、と言っているのであって、
「宇宙よお願い、私の代わりになんとかしてください、私、自分では何もしたくありません!」
と、信仰心ではなく依存心を持ってちょこっと気が向いたときにだけ神社に足を運び、
「これでなんとかしてもらえるよね?」
と思っていても、それは、
「私の代わりになんとかして~」
という依存心が強くなっていくだけで、信仰心は強くはならないです。
引き寄せはまず自分が変わることが条件の法則
…と、そんなことを言っている私ですが、私もあんまり人のことは言えなくて、もともとどうして引き寄せに興味を持ったかというと、
「叶うと信じればあなたの願いは叶います!」
と書いてある本を読んで、思いっきり、
「だったら、引き寄せってヤツが私の代わりに全部なんとかしてくれるってことか!」
と勘違いしたからです。
そう、自分では何もしなくてもよさそうだから、自分は一切変わらなくてすみそうだから興味を持ったんです。
こういう人って多いんじゃないかな?
正直、気持ちはわかります。
でも…よく考えてみてほしいんですけど、引き寄せって、
「叶うと信じればあなたの願いは叶います!」
ですよね。
これは裏を返すと、
「叶うと信じないならあなたの願いは叶いません」
ですよね。
ならば、いま「叶う」と思えていないなら、
まずそこから「叶うと思えるようになる」に自分を変える必要は絶対にあるわけで…。
つまり、まず最初に「自分が変わる」というのが絶対条件なんです。
自分は変わらないですむどころか、まず自分が変わらなければならない法則です。
しかしそう言われているっていうのになぜか、
「そうか、私は何もしなくていい!変わらなくていいんだ!」
と勘違いして依存心から飛びつく人が(私を含めて)多いように思います。
これは、
「えっ、違うじゃん。自分が変わらないとうまくいかない法則ってことじゃん」
ということに気づかない限り、効果が表れることはないと思います。
でも逆に言えば、変わりさえすれば絶対に効果は出ます。
宇宙にお願いするという方法で願いを叶えたいなら、まずは、
「依存するのではなく、信仰をするのだ」
「よし、ここから信仰心を持った人間に変わるぞ」
と決意すること。
そして、いかに宇宙が偉大かについて、しっかりと思考を巡らせること。
(そうして何度も思考を巡らせることはアファメーションに該当する行為)
それを続けていれば、おのずと信仰心も篤くなって信じられるようになります。
そうしてあなたが変わったならば、その変わった状態でお願いをするのであれば叶うんですよ、というのが引き寄せの法則です。
宇宙が叶えてくれるのは、あくまでも「あなたが宇宙を信仰する人間に変われば」の話。
依存心の強いまま変わらないでいても叶えてあげるね、とは言われていないですから、
信仰と依存を混同しないように気をつけてみてください。
宇宙にお願いしても効果がないのは、宇宙を信仰するのではなく依存しているから。
無料の動画講座を開催中です
引き寄せについて、さらに詳しく動画で学んでみませんか?
引き寄せで誤解しがちな点の解説や、願いが叶いやすい願望設定の仕方などについてお話しています。
動画の詳細については以下からどうぞ。
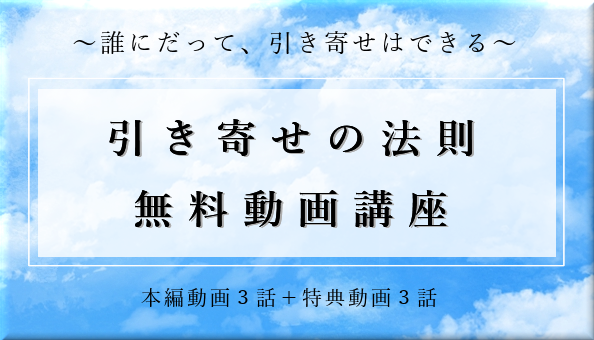

本日は、いただいた質問への回答です。
セルフイメージを上げるためにはどうすればいいですか?
2つ方法があります。
「とにかくやる」か「アファメーション」です。
セルフイメージを上げるにはアファメーションがおすすめ
セルフイメージとは、文字通りセルフ(自分)へのイメージのことですね。
このセルフイメージ、当然高いほうがいいですよね(*´ω`*)
セルフイメージを上げる一つ目の方法は、
「とにかくど根性で物事に挑戦する」
というもの。
無理やりにでも物事に取り組んでやってのければ、「俺はやったぞ!」とセルフイメージはあがります。
…でも、そんなど根性方式は嫌だと思う方がほとんどですよね(;^ω^)
もうひとつの方法のほうがおすすめです、それはアファメーション。
「私はできる、できる」
と繰り返すことで、潜在意識に「できるのだ」と学習をさせ、セルフイメージをあげていくやり方です。
アファメーションを1回しただけではセルフイメージは上がらない
これを聞いて、
「うむ、アファメーションかぁ…。
でもアファメーションって繰り返さないといけないし、面倒だな~…」
と思った方もいるかもしれませんね。
そう、アファメーションって何回もやらなきゃいけないのがちょっと面倒なところで、ついつい、
「私はできる!!ってこと、潜在意識に一発で学習させられたらいいのに…」
なんて思っちゃうかもしれません。
だけどこればっかりは残念だけど、無理なんです。
なぜかというと、そうやって1発で潜在意識が書き換わると危険だからです。
たとえばですが、
「火の中に飛び込んでも熱くない!!」
と1回言ったからって潜在意識が変わっちゃったら…、
それ以降、あなたは火を見ても怖いと感じることができなくなります。
これってすごく危険ですよね。
潜在意識はあまり賢くないので、言われたことが良いか悪いかという判断はできません。
そのため、
「もし危ないことだったら命にかかわるし、とりあえず物事は1発では覚えないでおこう」
という仕組みになっています。
それで少なくとも、有害な情報を一発で覚えちゃうことで起きる危険は回避できるし、
それでも何度も同じ情報が入ってくるなら、そこから徐々に潜在意識は、
「うーん、こんだけ繰り返されるんだから、きっと大事なことなんだろうな~。
大事なことなら覚えるかあ」
と変わっていく。
そういう仕組みになっているので、繰り返すしかないんです。
人は繰り返しによって新たな神経回路ができる
これを見ているあなたは、車の免許を持っているでしょうか?
持っているとしたら、最初に教習所で教わったときには上手に運転できなかったですよね。
最初の時点では潜在意識は、
「くるまのうんてんっていうのをすんの?
え?でも、良いか悪いかわかんない。危険かもしんない」
と警戒してます。
潜在意識が警戒している証拠として、はじめての運転の時には不安や緊張を感じたはずです。
けれど繰り返すことで徐々に、
「どうもコレ、安全っぽい。よし覚えるべか」
となる。
すると脳内に、徐々に「自動車の運転」に関する神経回路が出来上がってきます。
最初は細い神経回路なので、脳から「手をこういうふうに動かして」といった命令が下っても、
回路が細いためうまく伝達されない、なのでたどたどしい。
でも何度も繰り返しているうちにその神経回路は太くなり、脳からの指令がスムーズに伝わるようになる。
いまは完全にぶっとい回路ができてるので、指令もめっちゃスムーズ、考え事しながらでも運転できますよね。
セルフイメージを上げるのも運転と同じ要領
アファメーションでセルフイメージを上げるのも、これと全く同じ要領です。
まず、脳(潜在意識)に「私はできる」という新しい情報を入れはじめます。
この時点では潜在意識は、
「わたしはできる??
え?でも、できるようになるのが良いか悪いかわかんない。危険かもしんない」
と警戒してます。
潜在意識が警戒している証拠として、アファメーションをはじめてしばらくは、不安や緊張を感じます。
この不安や緊張を感じたときには、
「あぁ、警戒してんのね。
危険じゃないのに、危険かもしれないってビビってんだ、バカだな(笑)」
と思っておけばOKです。
よく、
「アファメーションをすると不安でたまらなくなります…」
というご相談をいただくこともありますが、
アファメーションの際の不安にはあまり本気になって構わないほうが良いです。
「潜在意識がちょっとアホなもんで、アファメーションが危険かもと勘違いしてオタオタしている」
以上の意味は全くもってない不安です。
真剣に「不安だ、どうしよう…」とか悩んで、潜在意識の勘違いに付き合ってあげてると効果が出るのが遅くなるので、
「アホだな~」と思っておけばOK(*^^)v
そのまま繰り返すことで徐々に、
「ほっ、どうもコレ、安全っぽい。よしほんなら覚えるべか」
となります。
そこから徐々に「私はできる」ということに関しての神経回路が太くなりはじめ、本当に自分にならできる気がしてくる。
つまり、セルフイメージが上がってきます。
そうすると、「どうせできないんじゃ…」とセルフイメージが低かったときよりもずっと物事に挑戦しやすくなります。
そして挑戦することできれば「私は挑戦できたぞ!」とさらにセルフイメージが上がりますよね。
ちょっと繰り返すのが面倒だとは思いますが、ど根性でセルフイメージを上げようとするよりも自然な感じで上がっていくと思います。
セルフイメージも運転も潜在意識にとっては同じ
ここで、
「…さっきからこの人、車の運転と同じ要領とか言ってんだけど、そんな単純か?
そこまで同じ要領で本当にセルフイメージって上がるのかな……」
と思ったかもしれませんが、
はい、そんな単純です。
そこまで同じ要領でうまくいきます。
「車の運転を覚えることとセルフイメージを上げることは違う」
と感じるのはあくまで顕在意識でのこと。
潜在意識はそこまで賢くありませんから、大きなことでも小さなことでも同じ。
良いことだろうが悪いことだろうが同じです。
すべて同じ要領でしか働かないのが潜在意識の特徴です。
なので、あなたが車の運転を覚えられたのなら、
同じ要領でセルフイメージも上げられますよ(*´ω`*)
無料の動画講座を開催中です
引き寄せについて、さらに詳しく動画で学んでみませんか?
引き寄せで誤解しがちな点の解説や、願いが叶いやすい願望設定の仕方などについてお話しています。
動画の詳細については以下からどうぞ。
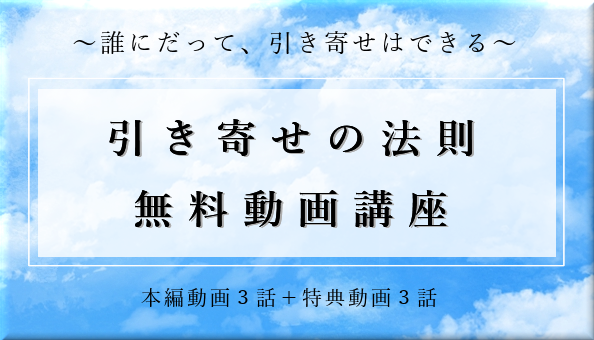

そもそも引き寄せでは、波動を上げることは必須条件ではない
本日は「波動」についてのお話です。
引き寄せでめっちゃよく言われてますよね。
波動を上げると良いことが起きるとか、質の低い波動を出していると悪いことを引き寄せるとか。
「でも、波動なんて見えるわけでもないし…うーん、本当に波動ってあるの?ないの?」
と思ってる人もいると思うので、これについて。
これ、もうハッキリいって「あるかないかなんて誰にもわからない」よね(;^ω^)
あるかもしれないし、ないかもしれないよね。
そんでもって、ぶっちゃけどっちでも引き寄せには関係ないです。
どっちでもいいので、無理には信じる必要はない。
「信じる必要はない」
ですから、
「信じてはいけない」
ではないですよ。
信じても信じなくてもどっちでもいいです、ということ。
波動って、信じてても信じてなくても引き寄せでうまくいくんです。
「信じない限り絶対にうまくいかない」
みたいに、波動を信じるという行為がうまくいくための「必須条件」ならば嫌でも信じる必要もあるだろうけど、そこは必須の過程ではない。
波動を信じないとうまくいかないと思い込んで必死に信じようとしている人も多いけど、別にそこは…あんま引き寄せと関係ないです。
波動を上げることは、目的ではなくて手段である
そもそも、波動を上げるって目的ではなく手段ですよね?
波動を上げる、という手段を用い、自分の人生を好転させる、ということが目的です。
裏を返せば「人生を好転させる」という目的を達成できるのであれば、
「波動を上げる」という手段にこだわる必要はないわけです。
引き寄せでよく言われますよね、「過程・手段にこだわるな」と。
私は波動にこだわるのは、過程にこだわることだと思います。
ここにこだわっているがためにうまくいかない人も多い。
「ええ…いや、波動は信じないとダメなんじゃないの?」
と思ってる方がいそうだけど、じゃあ、本当に心から波動を信じているAさんと、
「波動なんてないがな」と思っているBさんがいるとします。
2人とも、目的は「人生をうまくいかせること」です。
Aさんは「満月にお願いすると波動が上がります」と聞いて、実際にやってみた。
その結果、「ちゃんと私はやることをやった!これで私の人生うまくいく!」と思うことができて、前向きになった。
そして「うまくいく」という思考をもとに、うまくいくという現実につながった。
Bさんは私の記事に「自分との約束を守る」と書いてあるのを見て、実際にやってみた。
その結果、「ちゃんと私はやることをやった!これで私の人生うまくいく!」と思うことができて、前向きになった。
そして「うまくいく」という思考をもとに、うまくいくという現実につながった。
このように、「うまくいく」という思考さえ抱ければ、その思考を抱くための手段はなんでもいいです。
目的はあくまで「人生うまくいく」ことであり、そしてそのための必須条件は、
「人生うまくいくと思考すること」
です。
肝要なのは「うまくいくと信じられるか否か」というところであって、
「波動を信じて上げようとするか否か」というところではないんです。
人には性格、向き不向きがあるから、スピリチュアル的にとらえて、
「満月に祈ればいいんだ!なるほど!」
と思うことでそれが自信につながりうまくいくと思考できるようになる性格の人もいる。
逆にばりばりの理系の人とかなら、
「満月に祈ってうまくいくという科学的根拠はなんぞや…信じられへんがな」
とかどうしても思っちゃうだろうし、そういう性格の人は満月に祈るという方法ではうまくいかない。
そういう人には理論で説明したほうが「なるほど」と思うし、それで納得してうまくいくと思考できるようになります。
多くの人にある、霊的なものは「多少だけ」崇めるという信念
大概の日本人(いや日本人じゃなくてもそうか?でも外国のことを詳しく調べたことはないからわからない)は、
幼いころから「霊的なものを崇めるように」と刷り込まれています。
まだ年端もいかないころからお墓にお参りに連れていかれたり、神社にお参りに連れていかれたり、
ホラー映画を見たり、「悪いことすると罰が当たるよ」と言われたりするので、漠然と、
「霊的なものはあるのだ、ないがしろにすると怖いのだ」
と思っている人は多い。
私はあまりスピリチュアル的なものは信じてはいないけど、それでも、
「じゃ、信じてないならこの地蔵をぶっ壊してくれ。祟りとか信じてないんだしできるでしょ?」
とでも言われれば漠然と怖いしやりたくない。
幼少期からの「霊的なものをないがしろにしてはいけない」という刷り込みが私の中にあるからです。
(ただ、別に地蔵をぶっ壊せるようになる必要もないので、無理にその刷り込みを取る必要もないとは思うけど)
ここで私が地蔵ぶっ壊したら、
「あの人ヤバイ…おかしいんじゃないの…」
ってなりますわな(;^ω^)
しかしその反面、「霊的なものを深く崇めてはいけない」という刷り込みも受けているんです。
こちらもまた年端もいかないころから、
「あの人、○○宗教に入って熱心にお祈りしてるんだって、やば~い」
「幸運の壺?ウソウソ!そういうの信じる奴ってバカだよ!!」
「あの人霊感あるとか言ってる~、注目されたいだけじゃないの(笑)」
といった言葉にも触れる。
崇めなさいとは教えられつつも、しかし徹底的に霊的なものを信じる立場に立てばそれはそれで、
「あの人ヤバイ…おかしいんじゃないの…」
となる。
なので、多くの人の潜在意識には、
「霊的なものに本気では入れこむべからず、しかし多少は信じて崇めるべし」
というふうな信念ができています。
その「多少」というのがどの程度の度合いなのかは人によるけど、
あまり白黒つけてどっちかに偏ると「ヤバイ」となるので、
みんななんとなく両方のバランスを取ってうまくやっている。
潜在意識下で波動を「度が過ぎている」と判断している場合も
潜在意識の目的は、すでに刷り込まれて学習している、
「霊的なものに本気では入れこむべからず、しかし多少は信じて崇めるべし」
というものです。
なので、
「本気で入れ込んだときにはブレーキをかけて止めてあげよう」
「でも一切の信心を手放そうとすればそれも止めてあげよう」
と働いている状態です。
ここで、
「波動を信じて月に祈れ」
といったことを言われたとき、それが、
「それは多少信じて崇める行為だ。ご先祖さまを信じて仏壇に手を合わせるのと変わんないよね?おっけ~♪」
だと潜在意識に判断されれば、そこで潜在意識は止めてこないです。
なので、効果が得られる。
逆に、
「それは霊的なものに本気で入れ込む行為だ、○○宗教のヤバイ人がやってるのと変わんないんじゃ…」
みたいに潜在意識下で判断されると、効果が得られない。
「波動を信じているはずなのに、うまくいかない」
という人は多いんだけど、それはその人の中で、
「波動を信じる=霊的なものに偏りすぎ」
という判断が潜在意識下でなされているため、ブロックされてうまくいってない、ということです。
なので、同じ方法でも効果がある人とない人にわかれます。
まぁゴチャゴチャ書いたけど、
「もともと信心深い性格の人は効くだろうし、そうじゃない人は効きにくい」
ってことですね。
ただ「祟りは絶対ある。その祟りは絶対私にくる」とか信心深く信じてる人はうまくいかないだろうけど。
波動を上げることにするのか、しないのかの選択を
で、じゃあうまくいかない人はどうすればいいの?というと、
①「波動は絶対にあるんだ!!」と心から信じられるようになるまで、波動を強く信じようとする。
②「別に波動を信じなくてもいいなら信じないでおこうかな」と信じないようにする。
①と②、どっちでもいいです、どっち選んでもうまくいきます。
多くの人は、
「波動を信じて祈る!とかオーラの浄化!とか、
なんか…本当に心の底からは信じ切れなくて抵抗あるんだよな…。
…かといって、そんなの信じない!やらない!なんてハッキリ言うと、
それによって自分の人生がうまくいかなくなりそうで怖いし…、信じないのも抵抗ある…。
あぁ、信じるのも抵抗あるし信じないのも抵抗ある」
とどっちつかずなんですね。
目の前で道が分かれている、道が2本ある。
①と②のどっちの道を選んでもいいのに、どっちにしよう、どっちに行くのにも抵抗がある、
と動いてないのでそこで停滞して、「うまくいきません、どうすればいいのでしょうか」となる。
このどっちつかずの状態を解消するとうまくいきますよ。
で、この「どっちかにしろ」はもちろん、徹底的にどっちかに偏れって意味じゃないです。
「自分の中で折り合いをつけろ」ってことです。
波動を信じるなら科学的な話を一切するなとか、
波動を信じないなら霊的なことに一切関与するなとか、そんな極端なことが言いたいわけじゃないです、それ生き辛いわ~。
ということで、どっちを選ぶかは重要じゃありません。
「うまくいくと思えるか否か」が肝要なところ。
どっちを選ぼうが、「これでうまくいく」と思考できるのであれば、必ずその思考は現実になってあなたは幸せになります。
引き寄せは「思考が現実になる法則」です。
「波動を信じるとうまくいく法則」ではないし「波動を信じなければうまくいく法則」でもないです。
「波動を上げるか否か」は重要な点ではなく、「うまくいくと思考できるか否か」が大事。
無料の動画講座を開催中です
引き寄せについて、さらに詳しく動画で学んでみませんか?
引き寄せで誤解しがちな点の解説や、願いが叶いやすい願望設定の仕方などについてお話しています。
動画の詳細については以下からどうぞ。